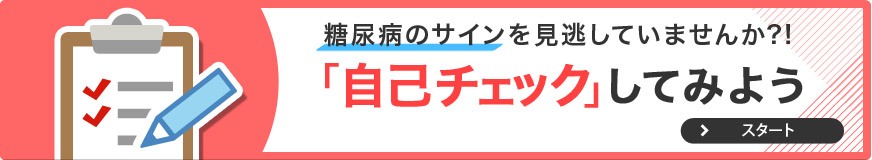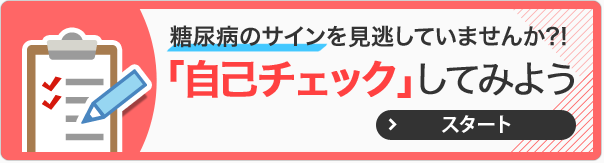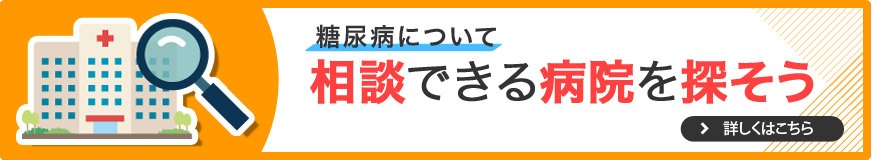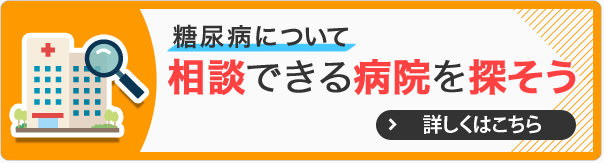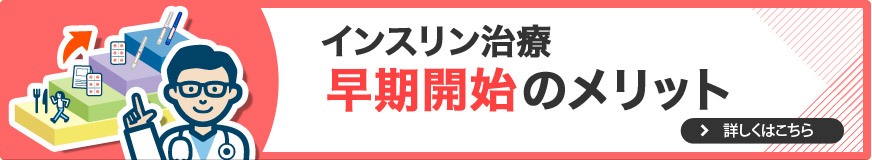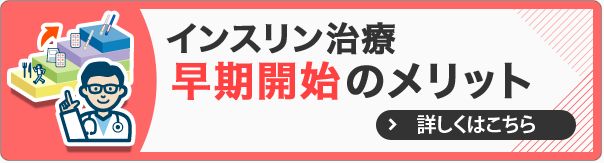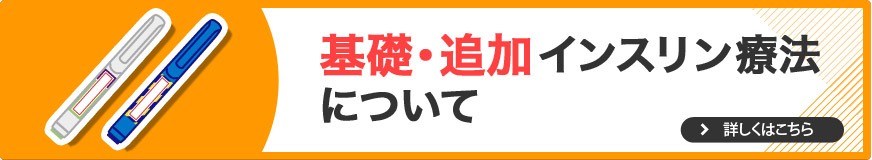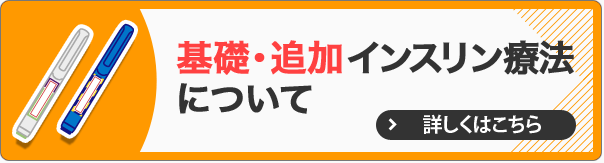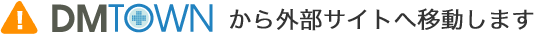経口血糖降下薬による治療
- ホーム
- 経口血糖降下薬による治療
- 経口血糖降下薬の種類
- インスリン抵抗性改善薬(チアゾリジン薬)
インスリン抵抗性改善薬(チアゾリジン薬)
どんな働きをするの?
インスリンは肝臓、骨格筋、脂肪組織で行われる糖代謝を促す働きがあり、これらの組織がブドウ糖を取り込んでエネルギーに利用したり、脂肪として蓄えたりすることで血糖の調整をしています。2型糖尿病ではインスリンの分泌の働きが弱まるタイプのほかに、インスリン抵抗性の状態にあるタイプもあります。インスリン抵抗性とは、すい臓からインスリンが血液中に分泌されていても肝臓、骨格筋、脂肪組織でのインスリンに対する反応が鈍くなっている(感受性低下)ために、インスリンの血糖を下げる働きが十分に発揮されない(インスリンの効きが悪い)状態のことをいいます。このインスリン抵抗性を引き起こす最大の要因は肥満であるといわれています。
インスリン抵抗性改善薬は、主に脂肪組織に働きかけて脂肪細胞から分泌されるインスリン抵抗性を引き起こす物質を減少させて、その名の通りインスリン抵抗性を改善することで血糖を下げる薬です。
どんな人に用いられる?
食事療法・運動療法がきちんとできているのに良好な血糖管理が得られず、インスリン抵抗性による高血糖がみられる場合に用いられます。肥満と高インスリン血症がみられる2型糖尿病に効果的とされていますが、肥満でない人に用いても血糖を改善する効果がみられることもあります。また、すでにSU薬などの服薬を行っている場合の併用薬としても用いられることもあります。
薬剤の種類は?
ピオグリタゾン塩酸塩があります。
薬剤は、医師が患者さんの糖尿病の状態をみながら、薬剤の働き(作用特性)を照らし合わせて最も適切なものを選択しています。
この薬剤を使う際に気をつけること・知っておきたいこと
- インスリン抵抗性改善薬を使う際には、食事療法・運動療法がきちんとできていることが特に重要となります。
特に食事療法がきちんとできずに過食傾向が続いている場合は、短期的に血糖管理の改善がみられても、肥満の有無を問わず次第に体重・体脂肪が増加してしまい、その結果インスリン抵抗性の状態に逆戻りして血糖管理が再び不良となることがあります。
インスリン抵抗性改善薬を用いる際には、体重が増加しやすい傾向がありますので、食事療法をきちんとすることがまず大切です。 - 肝機能障害をきたすことがありますので、もともと肝機能障害がある場合は定期的な肝機能検査が必要になります。重度な肝機能障害、肝炎や肝硬変などを合併している場合にはインスリン抵抗性改善薬は使用できません。
- 体内に水分が貯まりやすいため、心不全の合併や過去に心不全を起こしている場合にはインスリン抵抗性改善薬は使用できません。
- インスリン抵抗性改善薬にはインスリン分泌を刺激する働きがないため、インスリン抵抗性改善薬のみの服薬では低血糖は起きにくいとされています。その一方で、浮腫、貧血、血清LDH、血清CPKの上昇が認められることがあります。
血糖管理が上手くいかないとき
- 食事療法・運動療法がきちんとできていますか?
→管理不良の一番の原因です。再度、自分のライフスタイルを振り返ってみましょう。インスリン抵抗性改善薬は食事療法の代わりにはなりません。特に食事療法がきちんとできないまま漫然と服薬していると、最終的には糖尿病が悪化したり、動脈硬化症が進行することがあります。 - インスリンの分泌量の低下が起きている可能性があります。
→インスリンの分泌を促進する働きのある他の薬剤の併用や、切り替えが考慮されます。 - 糖尿病以外の病気が発症または悪化していることが考えられますので、定期的なチェックを受けるようにしましょう。
<各薬剤共通の注意点>
血糖管理がよくなったからといって自己判断で服薬を中止してしまうことは決してしないでください。血糖管理が順調なのは、食事療法・運動療法と、服薬している薬が上手く機能しているからです。薬の量を減らす、増やす、止めるなどの判断は、医師が患者さんの状態にあわせてその都度適切な処方をしていますので、必ず医師の指示に従うようにしましょう。
もし、今、服薬している薬について少しでも不安や疑問があれば、遠慮せずに主治医または薬剤師に相談するようにしましょう。安心して、信頼して薬が飲めることも、治療の継続と成功への大切な要素であることを知っておきましょう。
監修:順天堂大学 名誉教授 河盛 隆造 先生